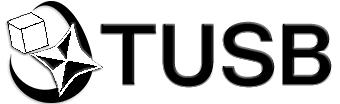Side Story of Item:賢者の杖の伝承(1)
[ガスト島内部 冒険者の拠点]
拠点では冒険者たちがせわしなく、島の攻略の準備を進めている。
その中でひとりの黒魔導士だけが、疑念を抱いた表情で机に向かっていた。
「うーん、やっぱりわかんない」
机の上に置かれた一本の杖を、黒魔導士はまじまじと眺める。
その杖の名は《古の杖》。黒魔導士が島の攻略をしている最中、道端の宝箱から拾った杖だった。試しに使用したら思った以上に高性能だったため、今の黒魔導士はこの杖を主に使用している。
「こんな文字、他のところで見たこともないし・・・」
しかし同時に、この杖の謎に黒魔導士は頭を悩まされていた。
村人製とは思えない奇妙な装飾。
彼女の知識にあるどの文字体系とも結びつかない、柄に刻まれた謎の文字。
欠損が多いにも関わらず、正常に魔術を行使できてしまう異常。
そんなこと気にせず使えばいい、とは本人も思っているのだが、
彼女の生来の探求精神、研究家気質がそれを許そうとしない。
だからこうして攻略にも行かず、一人でずっと悩んでいた。
「・・・・・・うん、ひとりで考えてちゃダメなのかも」
自分一人では解決できない問題だと悟った黒魔導士は、同じ魔導士に協力を仰ごうと思った。しかし白魔導士と召喚士は攻略の準備に忙しそうで、とても他事を頼めそうにない。
「交易島の村人さんになら、協力してもらえるかも・・・?」
交易島には、この空の世界に挑むものたちの協力者がいる。
彼らは商店を経営する身のはずなのに、不思議なことに全員が"村人"だと名乗る。ゆえに冒険者たちは、彼らをまとめて村人と呼んでいた。
彼らも魔王勢力と同じように不可解な存在で、黒魔導士としてはこの《古の杖》以上に謎めいた存在ではあるのだが、これまでの接触、交易の経験から、信頼できる存在ではあると思っている。
「よし、行こっか!」
村人たちの協力を得ることにした黒魔導士は、《古の杖》を片手に拠点を飛び出した。
随分と前に取り戻した青い空の下を、彼女は元気に駆けていく。
/
[交易島]
「・・・という事なんですけど、何か知りませんか?」
「いや、知らないねえ。他の変なものと同じように、遠くの世界から流れ着いたんじゃないのかい?」
黒魔導士は村人たちに聞いて回っているのだが、その成果は今のところ芳しくない。今はマツキヨと名乗る薬剤師の村人に、《古の杖》について知らないことがないか尋ねている。
「それはそうだと思うんですけど、作りそのものは職業装備に近いんですよ。それが奇妙で・・・」
「んー、うちは杖について詳しいことはよく知らないからね。そういうのは開発者に聞いたほうがいいんじゃないか?」
"開発者"という言葉を聞いて、黒魔導士は急に嫌そうな表情になる。
「・・・それって、あの人の事ですよね」
「ああ、ウルトラバイオレットなら頼りになるだろう」
ウルトラバイオレット。本名、ノート・パンジー。村人たちの中でも知識人として有名で、数多くの村人製アイテムの開発を手掛けた人。
しかし彼女は数年前のテーブルマウンテン上層への出張以降、明らか様子がおかしくなってしまい、村人や冒険者たちから語ることを憚られる存在でもあった。
「・・・・・・その、あの人はちょっと・・・近寄りがたいし・・・そもそも、全然飛空島に帰ってこないじゃないですか・・・」
「・・・まあ、確かに君の気持ちはわかるよ。でも多分、彼女しかこの問題は解決できない」
「確かにそう言われると、返す言葉もないです・・・・・・」
黒魔導士の言った"職業装備"もまた、元を返せばノート・パンジーが開発したアイテム。ただでさえ知識人である上に、求めている謎に近い位置にいる彼女に接触しない理由はない筈だっだ。
(でも、バイオレットさんだもんなあ・・・)
黒魔導士はどうしてもウルトラバイオレットへの嫌悪感が拭いきれないところを、それでも杖の謎を優先するべきだ、という意思で打ち負かそうと努力した。
黒魔導士は数分ほど悩んだ結果―
「・・・決めました。わたし、バイオレットさんを探してきます」
―意を決して、ノート・パンジーの下を訪ねることにした。
/
[ガスト島の拠点]
(・・・とは言っても、そう簡単じゃないんだよね)
黒魔導士はノート・パンジー捜索を決意したものの、その実行に踏み切れずにいた。
その理由はひとつ。
彼女が居ると推測されるテーブルマウンテン上層までの道は、まだ攻略されていない未知のエリア。黒魔導士ひとりで挑むには無謀すぎる場所だった。
(みんなが力を貸してくれたらいいんだけど・・・)
今は冒険者全員が島の攻略に繰り出していて、拠点の中に黒魔導士以外の人影はない。現状、通常世界の攻略を優先している方針もあり、すぐにテーブルマウンテンへ向かえるかは微妙な状況と言える。
(できれば魔導士ふたりが帰ってきてくれれば、とても良いんだけど・・・)
黒魔導士がそう思った瞬間、拠点のベッドの付近に手持ちを失った冒険者二人が現れた。
「あっ、黒魔ちゃん?」
二人のうちの一人、召喚士が黒魔導士に向かって声をかける。
「・・・!二人とも、帰ってきたんだ!」
「ええ。死に帰りですけどね」
「あたしたち、奈落に落とされちゃったのよ」
幸運なことに、黒魔導士が望んだ二人がちょうど拠点に帰還してきた。
島の攻略に失敗している二人にとっては、ある意味不運ではあったかもしれない。
/
「「・・・テーブルマウンテン?」」
「そう。5F以降の探索をしたいんだけど、二人はついて来てくれる?」
拠点の休憩スペースでくつろぐ二人に、黒魔導士は話を持ち掛けた。白魔導士は椅子に行儀よく座り、召喚士は黒曜石の床をごろごろと転がっている。
「テーブルってあの難しい所でしょう?あたしたちに行けるかしら」
「拠点の装備を失う心配がないという点では、良いかもしれませんが・・・」
二人ともその提案に賛成はしているものの、黒魔導士と同じように能力に不安があるようだった。
実際、この場にいる魔導士三人のLvは約23程度で、攻略に有用なスキルが揃っているとは言い辛い。加えて三人とも死に帰りに定評があり、これまで攻略にさほど貢献してこれなかった事実があった。
「うーん、やっぱり二人とも不安なのね」
「そうですね。5Fより上は溶岩地帯と聞きますし、私たちには危険ではないかと思うのです」
最もな意見だと黒魔導士は思った。事実、彼女たちよりLvの高い冒険者たちも、溶岩地帯を一目見た後に撤退を選んだ経緯がある。
もちろん、黒魔導士はそれでも行きたいと思っている。ただ、それだけでは二人が動く理由にならない。
(どうすれば、協力してもらえるのかな・・・?)
黒魔導士は思考を巡らせる。
(―わかった。二人には、テーブルマウンテンに向かう理由がない・・・ただの無謀な賭けになっちゃうんだ)
始まりはただの好奇心。あるいは謎を解明したい究明心。
白魔導士と召喚士には、黒魔導士にある"動機"が欠けていた。
(それなら、行きたいって思わせればいいんだ!)
少し邪な考えであることを自覚しつつも、黒魔導士は閃いたそれを実行に移すことにした。
「ねえ、白魔ちゃん」
「はい」
「わたしは、やっぱり勇気が大事だと思うよ」
「勇気・・・ですか?」
「"勇気ある者に栄光を"。テーブルマウンテンの碑文の一文だよ」
その言葉を口にする黒魔導士本人は、邪心ある者として天罰を受けることを恐れている。
「・・・確かに、失うことを恐れていては、何も始まりませんね。
私も臆病者から卒業して、立派に前線に立てるようになりたいです」
「うん。だから、一緒に行こう?」
「はい。黒魔ちゃんと一緒なら、きっと安心です」
「召喚士ちゃんも、みんなを見返したいって思わない?」
「・・・それは、思わなくも・・・ないけれど」
相変わらずごろごろと転がっている召喚士も、動機を刺激されて判断に悩んでいる。
「・・・ええ。仕方ないから、二人に付き合ってあげるわ!」
召喚士も若干ツンデレ風な口振りで、黒魔導士の提案に乗ることを選んだ。
「二人とも、ありがとね!」
/
[テーブルマウンテン ゲート前]
一日後。
魔導士三人は動機を胸に、テーブルマウンテンへ繋がるゲートの前に立つ。
愛用の杖は持ち込めなくても、多少なりとも積み上げて来た経験を手にして。
「みんな、覚悟はいい?」
「はい!」「ええ!」
「それじゃ、行くよ―!」
《古の杖》から始まった冒険は、まだスタート地点を過ぎたばかり。
黒魔導士 Lv:21
【アイスストームⅡ】【サンダーボルトⅠ】【ウェザー】【グロウ】
白魔導士 Lv:26
【ケアルⅢ】【ディアⅢ】【キアリク】【バオル】
召喚士 Lv:23
【あつあつタライ】【金タライ】【サモンE:マーチャント】【サモンE:スーパードラゴン】